今日の午前中は三原山のある建物へ行って、アシジロヒラフシアリの様子を見てきました。

あまりに凄すぎて、今回は負けそうです(悲)
それでも、建物周辺や中で、かなりの頭数が死んでいます。すぐ隣に大群が住んでいる状況では、対応が難しいですね。
今は、新しい実験を色々しています。

思いついたことを、すぐに実験できるって楽しいですね
上手くいきましたら、また、このブログで書こうと思います
話は変わって、今日はガイドの仕事をしてきました。
今日は、「2021年5月30日、東京都八丈島のヘゴの森ツアーの様子」と題してのお話です。
ヘゴの森の入口

今日は、女性2人のグループを案内しました。自然に興味があって、色々と回っているそうです。
ヘゴの森の入口は、このブログでも紹介していますね。この場所は、雑誌やTV、最近では、個人発信のYouTubeでも見られます。
イモリは繁殖期

今はイモリの繁殖期です。水辺ではイモリがたくさんいました。
お客様は、
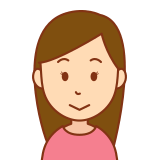
かわいいー
を連発していました。小川の水中を歩くイモリの様子が間近で見られます。
ヘゴの横断面の不思議

ヘゴは、木生シダですので、見た目は木です。でも、シダ植物ですので年輪はありません。
ヘゴの横断面に年輪がないことに、お客様は驚かれていました。
ヘゴの森を上から眺めました

ここはヘゴの森の撮影スポットですね。今日のヘゴの森の様子はこんな感じでした。
雨の日、霧の日とヘゴの森の様子はとても変わります。

ヘゴの森は、いつ来ても飽きないですね
ヘゴの森のジャングルの様子

ヘゴの森のツアーは、2 kmくらい歩きます。登山というよりは、ジャングルを歩くような感じです。
お客様は、ご自身が歩かれた道を振り返って、その鬱蒼としたジャングルに驚かれていました。
スギの木を枯らすフウトウカズラ

フウトウカズラはコショウ科に分類されます。でも、辛くありませんので、調味料としては使えません。
フウトウカズラがスギの木につきますと、スギの木はすぐに枯れて倒れてしまいます。写真では上の方が写っていませんが、すべて途中で折れています。フウトウカズラは、スギの木にとっては、とても恐ろしい植物です。
巨大なシダのリュウビンタイ

八丈島は年間3,000 mm雨が降ります。シダ植物の楽園のような土地です。
八丈島のシダ植物は、いずれも大きくなります。その中でも、リュウビンタイは大きい部類のシダ植物です。
シダ植物と聞きますと、足元に生えるというイメージがあります。リュウビンタイは、その基準を遥かに超えますので、お客様はとても驚かれていました。
もふもふの毛で覆われているヒカゲヘゴ

ヘゴは全身を大きな棘で覆われています。学名がCyathea spinulosaのとおり、棘があります。
ヘゴの森にはもう1つ木生シダがあります。

それが、ヒカゲヘゴです
ヒカゲヘゴは、棘が金色の毛に変わった木生シダです。お客様は、もふもふの金色の毛を触って、
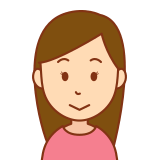
動物の毛みたい
と喜ばれていました。
シダに見えないマメヅタ

ヘゴの森は、散策路からたくさんのシダ植物が見られます。その中で、少し変わった形のシダ植物があります。

それがマメヅタです
マメヅタは、栄養葉と胞子葉の2種類の形態の葉を持っています。胞子葉は、その名の通り、胞子を作るのに特化した葉です。
ですので、マメヅタはシダ植物に分類されます。
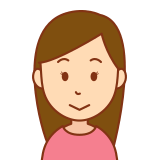
不思議〜
と言って撮影していました。
ヘゴの森のあとは、みはらしの湯へ行く予定だったそうです。諸事情により温泉は全てお休みですので、裏見ヶ滝へ行くと言っていました。
今は色々と難しいところがありますが、早く、八丈島旅行が普通に楽しめるようになるといいですね。




