寒波の影響から、ここ八丈島も気温がぐっと下がりました。
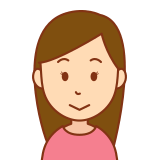
常春の島とよばれていますが、寒いですよね
実は、お客様からよくこのようなご感想をいただきます。南の島でも冬は寒いので、旅行の際は防寒対策はした方がいいと思います。
そんな八丈島です。今日も寒かったのですが、空はとても良い天気でした。

ヘゴの森ツアー日和ですね
今日は、「2022年1月4日、東京都八丈島のヘゴの森のツアーの様子」と題してのお話です。
久しぶりの英語でのガイド
今日のお客様は、日本語も大丈夫だったのですが、お話をしていると英語の方が楽しそうでしたので、8割を英語で説明しました。
いつもは予習してくるのですが、今日はぶっつけ本番です。けっこう忘れていますね(笑)。
ヘゴの森の植物には学名がついていますが、英語名は無いものはたくさんあります。

これらをどう説明したらいいのかなぁ・・・?
と思っていましたが、ツアー中、お客様と一緒に、それぞれの出身地、八丈富士のお鉢回り、なぜか阿倍野ハルカス、八丈島の生物の変遷など、いろいろなお話で盛り上がりました。

ヘゴの森の散策路全コースのツアーの様子
お二人は、木生シダのヘゴは初めてみたそうです。木ではないので、輪切りにしますと年輪は存在しません。

ヘゴの森のエリアは、ジェラシックパークに出てくるような木生シダが鬱蒼と茂っています。このながめに、お客様からも感嘆の声が漏れました。

やはり、今日はとても良い天気でしたので、ヘゴの森のエリアも青空で映えますね。

スギの木の墓場のエリアに来ました。フウトウカズラに包まれたスギの木はすべて倒れてしまいます。お客様は、樹皮がスカスカになっている部分を直接ご確認されていました。

今の時期、八丈島の森に入りますと、きれいな赤い実をたくさんつけた植物と出会います。
これはアオノクマタケランといって、文字通り、6月にはランのような花をつけます。八丈島では、お寿司やケーキの下に敷いたりしますね。

お客様は、ヒカゲヘゴの新芽を見ています。3億年前の化石からも見つかっているこの植物の新芽は食べられます。

生きた化石ともよばれていますね

当たり前ですが、日本で旅行をしますと、すべてが日本語ですね。
でも、私がアメリカに住んでいたとき、すべてが英語でした。日本語を聴いたときは、とても嬉しかったことを思いだしました。
今日は、ヘゴの森の植物の説明というよりも、英語での会話を楽しみながら散策したというツアーでした。お客様も楽しまれたようでした。

今日は、ヘゴの森へいらしていただいて、ありがとうございました




