最近は写真の機材関係でこのブログにたどり着いた方が多いみたいです。
私が初心者だったとき、カメラやレンズの選び方が分からず、遠回りをした経験があります。

当時は写真雑誌の存在さえ知らなかったですからね(苦笑)
さて、私自身も何でも撮影しているわけではなく、被写体が偏っています。ただ、長年写真を撮影していますと、

このシーンはこの機材で・・・。
というのは決まっています。
写真機材は高価です。購入の失敗が少なくなるよう、参考になればと幸いです。
今日は、「被写体別写真機材の選び方について ー日常編ー」と題してのお話です。
携帯で撮影しているのが日常の被写体
私たちが日常で見えるもの。最初にこれらを写真に撮ってみたいと思うのではないでしょうか?
携帯が撮影した写真は、最初に動画を撮影し、ピントが合っているところを切り抜きして、重ね合成して作られています。

よく出来ていますね

カメラを購入するタイミング
写真機材は、私は信頼できるお店から中古の物を購入することをおすすめしています。

新品は高いですからね(悲)
携帯はとても便利です。コンパクトなのでフットワークも軽いです。
ただ、コンパクトすぎるためにイメージセンサーとレンズの口径が小さいです。そのため撮影された写真の解像度が犠牲となります。
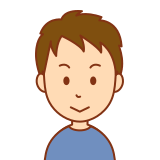
もっと良い写真が欲しいなぁ・・・
と写真に興味を持ち始めた人には物足りなくなってしまいますね。その必要性があったときが最初の一眼レフあるいはミラーレスカメラとレンズの購入タイミングとなるわけです。
カメラ、メーカーの選び方
カメラ選びの基本は、マニュアル露出をする際にダイヤル操作が出来ることです。写真を撮っていますと、最終的にマニュアル露出しか使わなくなりますので、これが必須です。
湿度の低いところで撮影する方は気にすることはありませんが、霧の中や雨の中で撮影することがある方は防塵防滴の機種を選んでください。

次にメーカー。日本のメーカーならば、どのメーカーでも大丈夫です。ただ、それぞれのメーカーには特徴があります。
Sony、Canon、Nikon、Fujifilmは、フルサイズのイメージセンサーを持つカメラを出しています。Fujifilmの場合は、フルサイズの1.7倍のイメージセンサーを搭載しているGFXシステムというのもあります。
Sonyは多くの機種が同じ形ですので、将来的にカメラをステップアップした時に違和感なく操作が出来ます。
CanonとNikonはだいたい同じくらいのレベルです。両メーカーとも老舗ですので、中古レンズがたくさんあり、レンズの選択肢が豊富です。
Olympus Digital Slutionsは、マイクロフォーサーズサイズのイメージセンサーを採用しています。
小型、軽量、防塵防滴です。少しでも写真機材をコンパクトにしたい方に向いています。
Fujifilmは、元々フイルムメーカーだったこともあり、色の発色にこだわりがあります。風景写真と言えばこのメーカーでしょう。



最初は焦点距離24-105 mmのズームレンズ1本で
焦点距離24-105 mmのズームレンズは、携帯のレンズで撮影出来る画角を全てカバー出来ると思います。中古であっても最近のレンズには手ぶれ補正機能が付いており、初心者でも扱いやすいです。
ただ、最高級のズームレンズを除いて、ズームレンズは1本で全ての画角をカバーする利便性から画質が単焦点のレンズよりも少し劣っています。私の場合は、ピントの合う範囲を広げるために大きな絞り値を選択して使っています。

これだけでパッと見、画質の粗が目立たなくなります
発展編
写真分野にはスナップというものがあります。カメラを片手に、
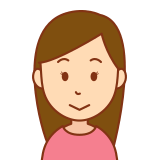
あっ、これ、いいかも・・・
と自分の直感的な気持ちにしたがってそのまま撮影する方法です。
ズームレンズですと、物理的にレンズのサイズが大きいので反応が鈍ります。そこで、スナップ写真を撮る多くの方々は、焦点距離28 mm(携帯と同じ画角)あるいは35 mm(肉眼と同じ画角)の広角系の単焦点レンズを使っています。
単焦点レンズを使う利点は、
- ズームレンズより価格が安い。
- 画質がいい。
- 小型軽量でシンプルな操作性から速写性が高い。
です。焦点距離24-105mmのレンズの画角で満足される方であれば、この広角系の単焦点レンズ1本あれば、これ以上追加のレンズは必要ないかも知れませんね。
上述の焦点距離28 mm、35 mmの単焦点レンズは各メーカーから出ています。

私は、レンズ沼には入らなくてい良いという考え方を推奨しています(笑)

今日は、「被写体別写真機材の選び方について ー日常編ー」と題してのお話でした。
日常の被写体の紹介、携帯と一眼レフあるいはミラーレスカメラとの違い、カメラの選び方、メーカーの選び方、焦点距離24-105mmズームレンズ、焦点距離28 mm、35 mm単焦点レンズの紹介をしました。

参考になれば幸いです
PR




