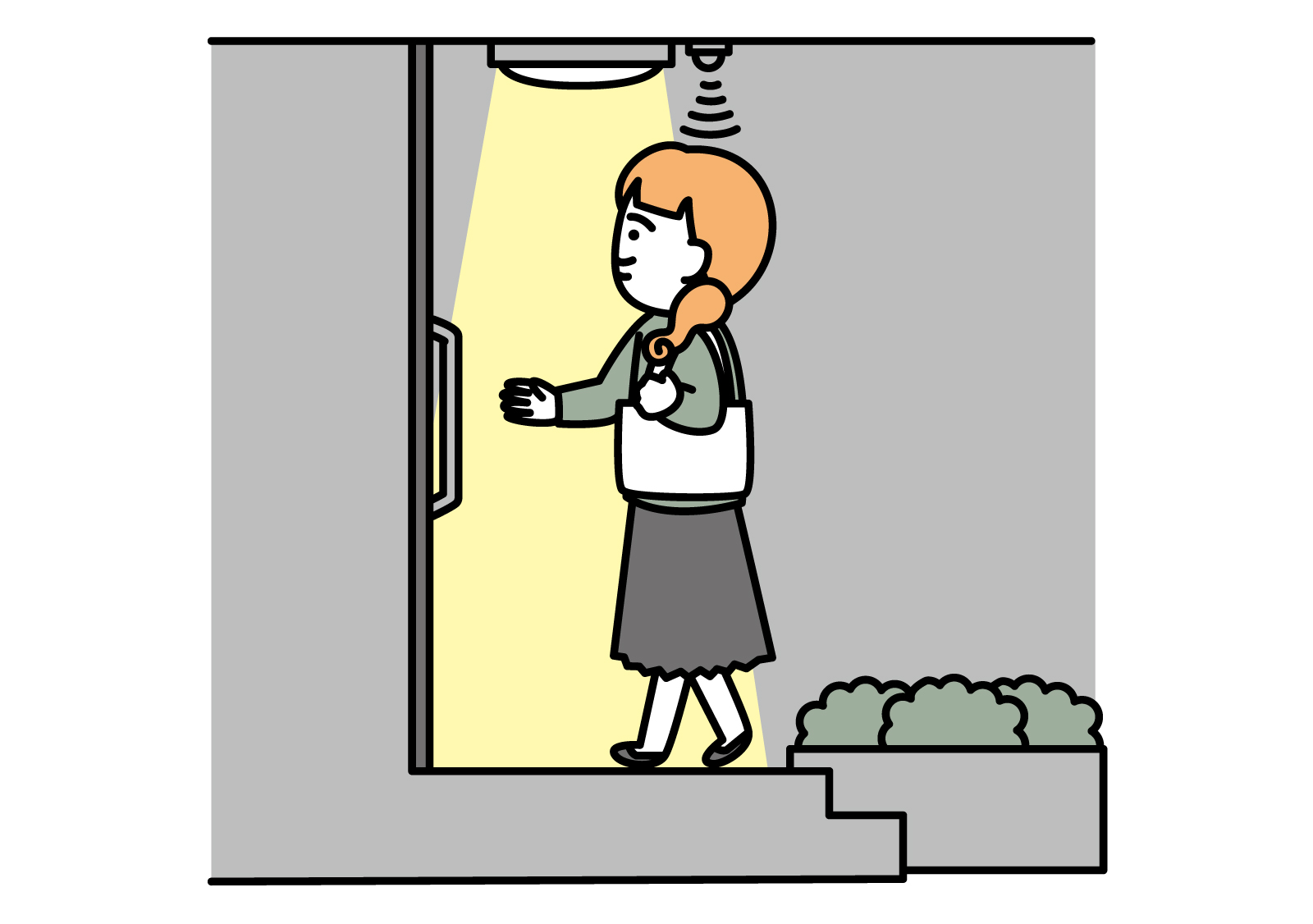2025年春、東京都八丈島で野鳥の水浴びの撮影を計画し、これまで人工の水飲み場を準備し、夏には野鳥が来るようになりました。
現在は、野鳥のリモートコントロールによる無人撮影を計画し、そのために必要なモニター機材のテストをしています。
野鳥を撮影する時、一瞬が勝負になります。成否は集中力に依存します。
ところが、人はずっと集中することは出来ずどこかで間が空いてしまいます。

そういう時に限ってシャッターチャンスが来るんですよね
人は機械ではありません。人側の努力ではこの問題の解決は出来ないように思えました。

何か良い方法はないかなぁ・・・
と、Amazonを眺めていましたら面白い物に目が留まりました。
PR

今日は、「人工の水飲み場で人感センサーが野鳥を検出出来るかどうかテストしました」と題してのお話です。
野鳥の出現を音で知る
昔読んだ宮崎学先生の「フクロウ」の制作秘話に、止まり木にセンサーを仕掛け、一晩で何回利用したかを自動記録してデータを集めたという行がありました。各枝にはそれぞれのセンサーが仕掛け、枝ごとに違う音でアラームを鳴らし区別したそうです。
お店に入りますとセンサーが働き入口でピンポーンと鳴るのは今では普通のこと。水飲み場に野鳥が来たら、同じように音で知らせてもらえればいいはず。
直前まで休めていますので、呼び鈴以降は集中してカメラのシャッターを切れると思いました。
PR
人感センサー
私は宮崎学先生のようには自作は出来ません。でも、2025年なら私の目的に合ったものがあるはずです。

そして、見つかったのがCallToU社製の人感センサーです
これは介護用に設計されたものです。送信機の人感センサーに人が近づきますと、受信機が鳴り、振動します。動作距離は屋外で150 m、屋内は90 m。
使い方はとてもシンプル。人感センサーの送信機と受信機に電池を入れ、受信機は好みの音と音量設定するだけです。
PR
人感センサーのフィールドテストの準備
音が鳴りますと野鳥が逃げてしまうことがあります。人感センサーの受信機の設定は、音量をゼロにし、振動だけにしました。
今回は、送信機の人感センサーが野鳥を検出し、実際に受信機に知らせられるかどうかを調査しました。野鳥が人工の水飲み場に出現した時間はトレイルカメラで、受信機の動作の時間は自分で記録しました。

人感センサーのフィールドテストの結果
テストは2025年7月19日。私は人工の水飲み場から30 m以上離れた野鳥からは死角の場所に隠れていました。
14:55~14:58まで連続して受信機が鳴りました。双眼鏡で見ますと人工の水飲み場付近にはホオジロがいました。
ホオジロが去った後、トレイルカメラを回収しました。そうしますと、確かに14:55~14:58までホオジロが記録されていました。
初めはオスのみ、最後の方はメスも人工の水飲み場に現れていました。
結論として、人感センサーはホオジロのような小型の野鳥を検出出来、自身の目的に利用できることが分かりました。
また、今回、これまでの人工の水飲み場と違って本番に近い形に石を配置しました。
滞在の連続写真から気づいたことは、ホオジロのような小さな野鳥は中心に止まれるような小さな石が有ったほうが落ち着くようでした。

撮影までまた一歩前進しましたね


今日は、「人工の水飲み場で人感センサーが野鳥を検出出来るかどうかテストしました」と題してのお話です。
人感センサーに注目した理由、フィールドでのテストの準備とその結果についてのお話でした。
初めは撮影まで簡単に進めると思っていたのですが、頭で考えたことと実践は違いますね。
今では、思い通りにいったり、思いがけないトラブルになったりする時間そのものが楽しく感じられるようになってきました。

今しか出来ないことが今出来ることに幸せを感じています
PR