私は過去に色々な箇所の骨を骨折してきました。
右腕(手術による切断も含む)、右手首、右足、肋骨、首、腰の骨、そして、今回の左足首です
当然ながら、治療のためにギプスをしました。
右足も交通事故の時に骨折を経験しています。ギプスによる肉体的不便さと精神的苦痛は分かっているつもりでしたが、何故か今回の左足首はときどき我慢出来なくなりました。

そう言えば、交通事故の後から、私はずっと1日中細かく起きたり寝たりの繰り返しの生活になったっけ・・・
自身の特徴的な睡眠を思い出し、そんなことならと一晩中起きることにしました。

快適になりました(笑)
それでも、本を読んだり、YouTubeを読んだりしても永遠に続けることは出来ません。

まとまった時間が出来たのだから、これからの撮影のことも考えるか・・・
新たな欲求が生まれました。
今日は、「ギプスで動けない間、自動撮影用の機材のアイディアを色々考えています」と題してのお話です。
YouTubeで写真家の宮崎学先生関連の動画を検索
私は昔から宮崎学先生の作品を見てきました。しかし、どうやって撮影したのか分からなかった写真もたくさんありました。
以前、宮崎学先生の本を紹介しました。
僅かな情報ですが、掲載されている写真、肉筆の中から、たくさんのヒントをいただきました。それらのヒントを元に無人撮影をしたのが、ホオジロとヒヨドリの水浴びの写真です。
ここでは、ポータブル電源、CCDカメラ、人感センサー、モニター、リモートコントロールを組み合わせました。
私が手に入れられる情報はまだあるはず。YouTubeで検索しますと、宮崎学先生のいくつかの動画が見つかりました。
動物に対する接し方や考え方は人の核心部分ですのでコピーは出来ません。しかし、撮影機材は、全く同じことは出来なくても、近いことは出来るはずです。
本に掲載された中古のカメラとフラッシュ、ハウジング、ケーブル、センサー、それらを支える三脚の写真を見て、

今の私なら出来るかも・・・?
とモチベーションが高まりました。

未知の世界は時間が経過すると解決していることもある
自動撮影装置を作るために、初めは昔のようにセンサーを自作するのかと思っていました。その他にも、

電源は?

ケーブルは?

レリーズは?

スリープした機材はどのように復活させる?
などの課題がありました。このこともあって、私は昔の自動撮影機材を復活させなかったのでした。
また、電気関係に詳しくない私は、今、自動撮影システムを構築出来るかも不安でした。
そんな時、YouTubeで電気工作関係の動画がたまたま入ってきました。そこで分かったこと、
- センサーは完成された既製品のようなパーツがある。
- センサーは特性によって複数種存在している。
- 昔のセンサーは単体でスイッチも兼ねていたものもあったが、リレーと合わせて使った方が良い。
- ケーブルは目的によって使い分けなければならないし、その基準がある。
- ケーブルの接続ははんだごて以外の方法がある。
- などなど
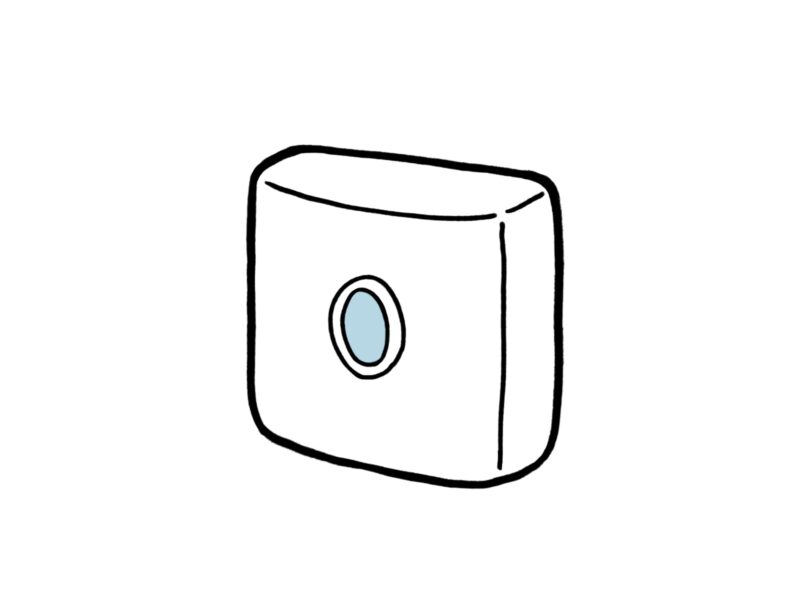
起きたり寝たりを繰り返しますと、そのアイディアが形になっていきます。起きたら、部品を調べ、夢の中でその部品を並べ、ケーブルで繋ぎ、不具合があったら一度解いて、また繋ぎ直していきます。
何度も繰り返します。
そして、また寝てまた起きて、その繋がったセットがハウジングの中に入っていきます。
知識はYouTubeからのみでは不安です。どこかで書籍を読む必要があると思い、下記の本を一通り読みました。
PR
昔の考え方と今のやり方が繋がっていきました。
自動撮影の予算は意外と安い
先日の無人撮影のセットを組む時は全て既製品を使いました。手持ちの機材を除きますと、全部で6万円くらいかかりました。
晴れの日限定で使用するのならば、EOS R3を使えば望遠レンズを使ってのAFでの無人撮影が可能となりました。
一方、自動撮影では、組み上げたセットは八丈島の過酷な自然の中で置きっぱなしになります。壊れる可能性はとても高いため、基本的に安価なパーツで、さらにハウジングを自作しなければなりません。
一見、大変そうに見えます。
予算を計算してみますと、家にあるものを除き、新たに中古のカメラとレンズ、パーツや器具を揃えますと、新品のミラーレスカメラを買うよりもずっと安く済むことが分かりました。
私が長年夢に描いた世界は意外と私の近くにあることを認識しました。
頭や言葉で描いていることは所詮空想です。研究と同様に、実践は違います。
自身が手を動かして初めて、自身が目指す世界と繋がります。

挑戦出来る人生って本当に面白いですね

早く足が治って欲しいと切実に思いました

今日は、「ギプスで動けない間、自動撮影用の機材のアイディアを色々考えています」と題してのお話でした。
様々なYouTube、本からアイディアを貰い、想像しながら、自動撮影の機材の原理、パーツ、組み立て方を想像しています。
案の形が繰り返し描くことで、想像の精度が上がりました。

早く怪我を治して、色々試したいですね
PR





